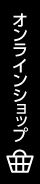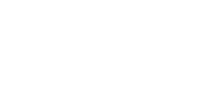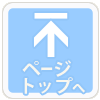- 仏教がなかったら
-
もしもこの日本から仏教の彩りや匂いが消えてしまったら、どういうことになるだろう。
我々の生活はよほど寂しく、貧しいものになるにちがいない。
まず山あいのお寺の鐘の響きが、聞こえてくることがなくなるだろうし、除夜の鐘にじっと耳をすます風物詩も姿を消してしまうはずだ。
お彼岸やお盆の季節に、ふるさとの墓前にぬかずいて、香華をたむける風景も見られなくなる。
肉親の死にさいして、無常の理を悟るという機会もおそらく訪れることがない。
我々をとりまく近代的で快適な生活を味わいながらも、疲れ切った神経を茶の湯や活け花によって慰めるといった風流も、おそらくままならないものになるだろう。 さらにいえば、もしも仏教の無常感覚や浄土イメージが我々の血流のなかに流れていなかったとしたら、「源氏物語」の「もののあわれ」の情調は、よほど貧寒としたものになったはずであり、「平家物語」の滅びの美学も生まれなかったにちがいない。
そのすべてが、仏教の豊かな水脈のなかから汲み出されていたのである。
この悩み多い現代社会の中で、我々は今こそ、仏教のこころを見直すべき時にきているのではないでしょうか。 - 生老病死
-
これまで、多くの日本人は死を「忌み嫌うべきもの」として遠ざけてきました。
しかし、以前なら子育てが終わる頃には人生も終末に近づいていましたが、現在は高齢化が急速に進行し、否応なしに自らの老いや死を考えざるを得なくなりました。
生まれなければ死ぬことはありませんし、生まれた生命はいつかは必ず死にます。
人は必ず死ぬという現実から目をそらしている限り、生を大切にすることはできないのではないでしょうか。
仏教の教えを説いたお釈迦さまが出家を決意した理由は、自分の力ではどうにもできない「生老病死 」という生の根源的な問題の解決をめざしたからだといわれています。 お釈迦さまは、生まれた生命は必ず死ぬという現実を直視し、死を鏡として私たちの生き方を示しています。
ですから、肉親や知人の死を通じて自分の生き方を考えるために、葬儀や法事などの行事が仏教の教えと結びついて行われているのです。 - 六波羅蜜
-
仏教では、「
六波羅蜜 」という六つの修行を説いています。
人間性を高める為の六つの教えです。- 「
布施 」 人を助け世のために尽くすこと - 「
持戒 」 人としてやってはいけない事はやらない - 「
精進 」 一生懸命努力を続けること - 「
忍辱 」 困難に耐えること - 「
禅定 」 心静かに自分を見つめること - 「
智慧 」 原理原則を理解しそれに従うこと
迷い、挫折し、先行きが見えないと思った時、今の自分はどうすれば良いか。 こういう教えが力を貸してくれます。
- 「
- 利他
-
成功を収めている企業人に必ず共通しているのは、「
利他 」の心をいつも内に秘めていることです。
「利他」の心とは、人を思いやる心。
自分だけの利益を考えるのではなく、自己犠牲を払ってでも相手に尽くそうという、人間として最も尊く美しい心です。
わが社にとってどうすれば利益になるとか、私個人にとって何が良いかということではありません。それは、一つの企業とか個人の利害得失を超えて、もっと広く高く、人間にとって、世の中にとって何が良いことなのかを考える生き方です。 - 慈悲
-
仏教には慈悲という愛があります。
慈悲は、神や仏の我々に対する愛、また、昔は親の子供に対する愛をさしました。
神や仏は目で見ることができません。これら目に見えないものの大いなる愛を慈悲、または慈愛と呼んでいます。
慈悲は与えるばかりで、お返しを求めません。あげっ放しの無償の愛です。
目に見えない大いなるものの愛は、慈悲を与えたことで、相手が少しでも苦しみから逃れ、心が癒されればいいと思うばかりなのです。
これはボランティアの精神にも通じるもので、ボランティアは奉仕するだけで、その奉仕に対する報酬や賞賛を相手から求めません。 - 煩悩
-
煩悩というのは、人間がもっている欲望のことです。
あれが欲しい、これが欲しい、あの人が羨ましい、こういうのは全部煩悩です。
大晦日に除夜の鐘を百八つ撞きます。百八つは我々の煩悩の数といわれていますが、これは仏教の用語で、算数的な百八つではなくて、無限の無限ということです。
働いている人が、お金を欲しいと思うのは当たり前ですし、名誉も権力を欲しいでしょう。人はそういう煩悩をバネにして生きているわけです。
欲望があるから人間なので、すべての人が全部セックスをしなくなれば、人類は滅びます。
しかし、欲望を欲望のままにのさばらせたら、それは無残なことになります。
欲望を上手にコントロールする知恵を養うのが仏教なのです。 - 四苦八苦と八正道
-
人生では
生老病死 の四苦の他に、まだ四つの苦があります。
愛別離苦 、怨憎会苦 、求不得苦 、五蘊盛苦 といわれます。
この四つと前の四苦を合わせて、四苦八苦と呼んでいます。
愛別離苦とは、愛する人と別れる苦しみ。
怨憎会苦は、怨み憎む者とこの世で会わなければならぬ苦しみ。
求不得苦は、欲しいものが手に入らない苦しみ。
五蘊盛苦は、人間の体や心の欲望が適えられない苦しみです。
この八苦は、生きているかぎりついて廻り、この苦から逃れるには、仏法僧 の三宝 に帰依 して、八正道 を実践するしかないと仏教は教えています。
八正道とは、お釈迦さまの最初の説法において説かれたとされる、修行の基本となる八種の実践徳目です。
それは、正見(正しい見方)、正思(正しい考え方)、正語(正しい言葉)、正業(正しい行い)、正命(正しい生活)、正精進(正しい努力)、正念(正しい意識)、正定(正しい精神の安定)の八つです。 - 愛憎
-
仏教の八苦の中に「
怨憎会苦 」というのがあります。
怨 み憎む者に会う苦しみです。
自分を憎み、嫌いだという相手への思いは、必ず相手にも反映して、自分のことを憎み、嫌います。
相手がなぜ自分にとって嫌いなことをするのかということを考え、相手の立場に立って想像力を働かせれば、その人が、生まれつき愛されない環境に育ったとか、あるいは、ずっといじめられてきたとか、欲求不満の固まりであるとか、そういうことがわかります。
そうすれば、ただ憎むよりも哀れみを感じることができます。
憎しみを哀れみに変えることが出来れば、自分も救われます。